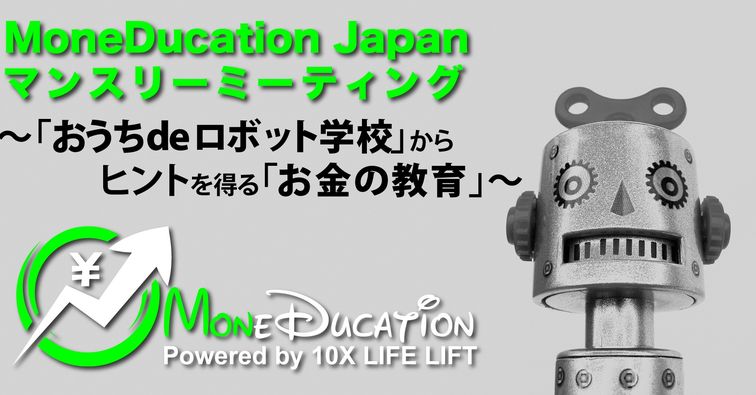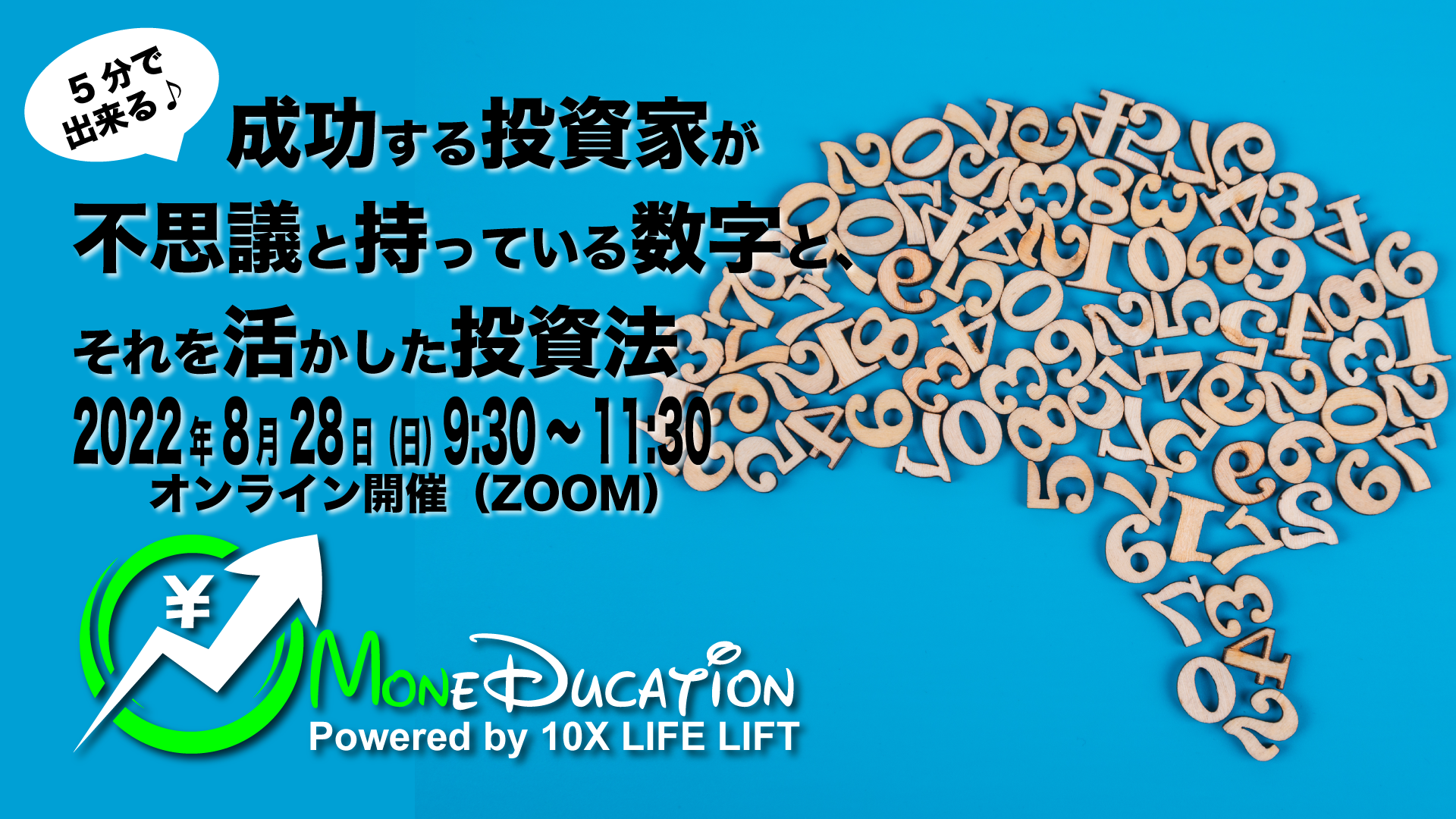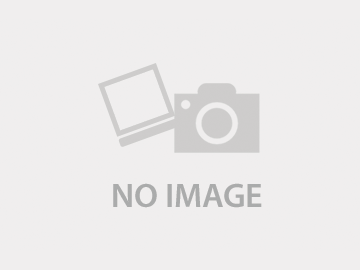マールアラーゴ合意、福音にも-国際金融のトリレンマに苦しむアジア
記事を要約すると以下のとおり。
アジアで一部の中央銀行が、経済理論の痛みを伴う再学習を強いられている。インドでは今年に入り、翌日物の借り入れコストが急速に膨らんだ。最初に銀行間金利の上昇は手元資金が不足している兆候で、より広範な経済に打撃を与える可能性がある。 国際金融のトリレンマは、新興国で保有する株式や債券の価値を直撃するが、一方で為替相場の安定が経済成長の犠牲を伴うものであれば、投資全体が損なわれかねない。インド準備銀行は本土内でのデフレ圧力という逆風に見舞われているにもかかわらず、人民元相場に焦点を絞り、これまでのところ大規模な流動性供給には踏み切っていない。 インドネシア中銀は自国通貨防衛で新しいアプローチを採用。 マレーシア中銀は通貨先物を活用してリンギットを支えているが、ロベコのマクニコラス氏によると、これは預貸率の高さと相まって、銀行間での流動性を逼迫させている。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース マールアラーゴ合意、福音にも-国際金融のトリレンマに苦しむアジア