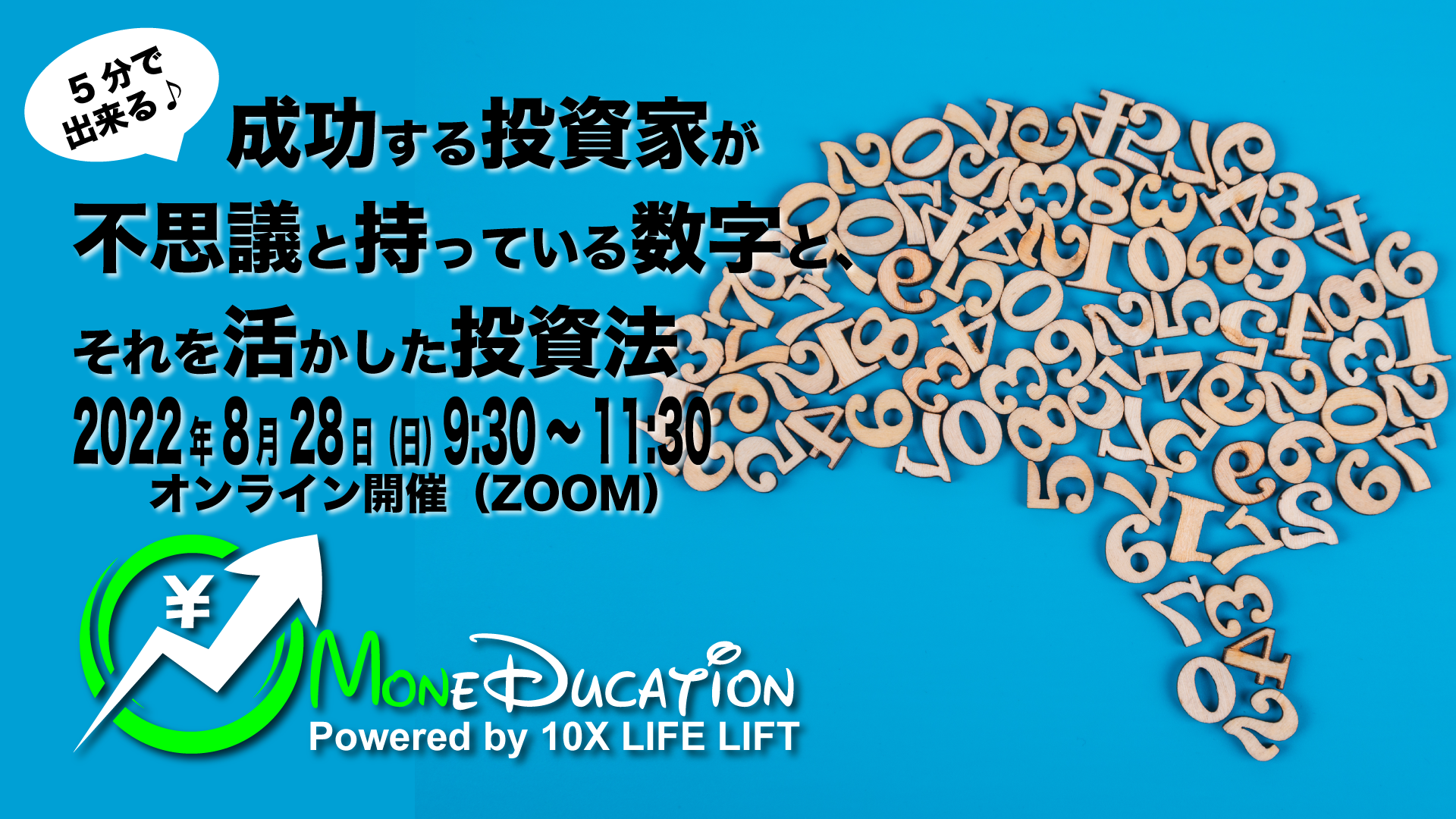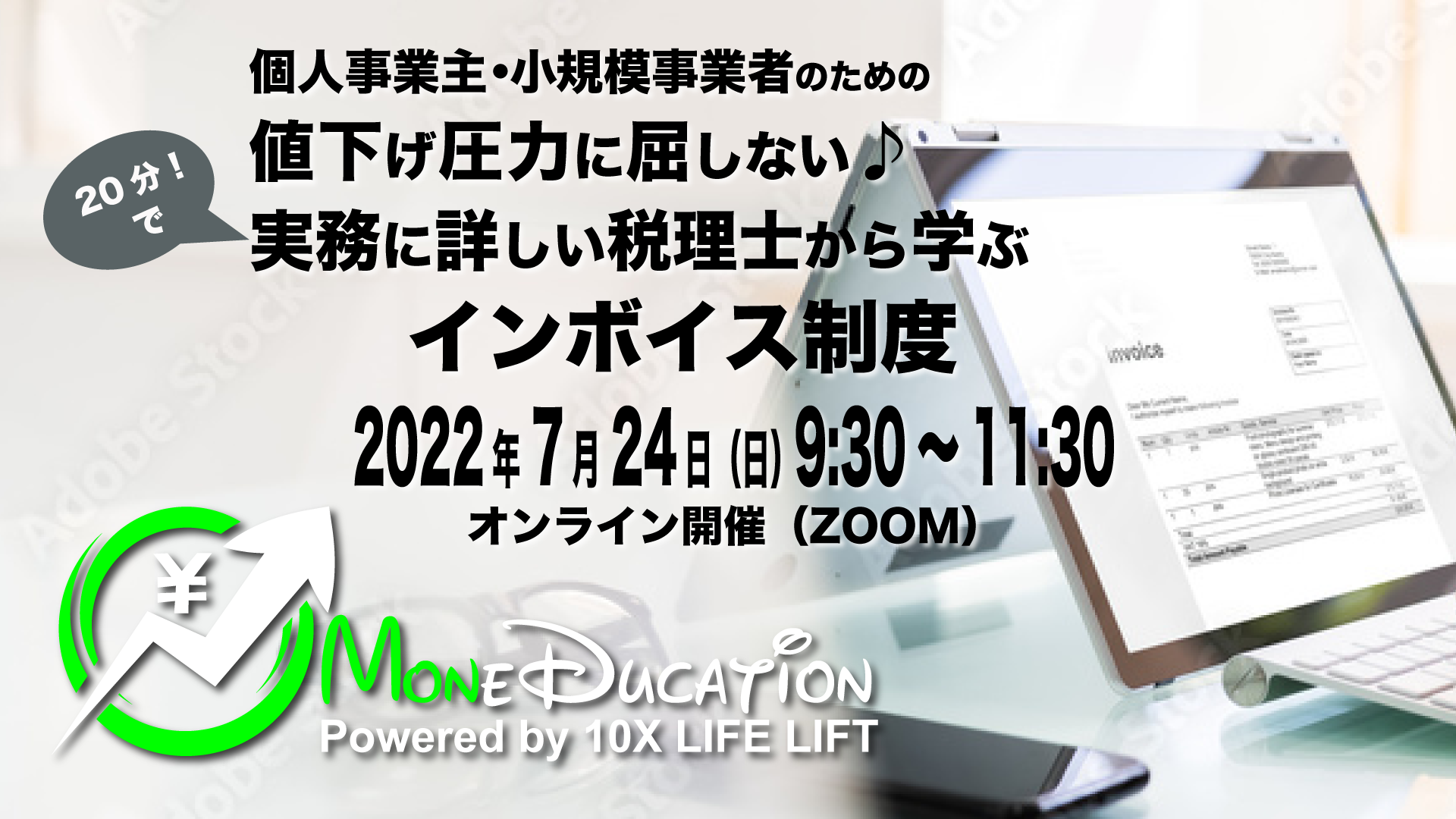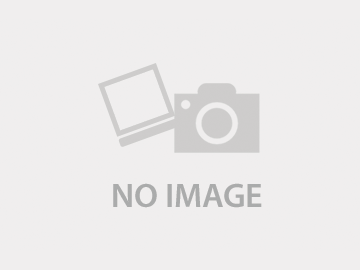日中関係の緊張続く、経済活動への波及リスク高まる-QuickTake
記事を要約すると以下のとおり。
日本と中国はアジアの二大経済大国であり、域内最大の貿易相手国同士だ。これを受けて日中間の緊張が高まった。 外交的な対立が激化する中、中国は何世紀にもわたり、北東アジアにおける政治・文化の二大勢力として存在してきた。 日本は中国の一部を侵略・併合し、1930年代から第2次世界大戦にかけては、南京事件などを含む軍事行動を展開した。東シナ海に浮かぶ尖閣諸島の一部国有化を決定して以降、中国はほぼ毎日のように海警局などの公船を周辺海域に送り込んでいる。中国船の侵入回数は24年に過去最多を記録した。中国はロシアとの間で軍事協力の強化を進め、両国は海軍・空軍による共同演習を日本周辺で行っている。22年に閣議決定した5年間の防衛力整備計画では、防衛費総額を約43兆円とし、対国内総生産(GDP)比で従来の1%超から2年前倒しで増額する方針を示している。尖閣諸島(中国名・釣魚島)Source:KyodoNews/APPhoto 24年には中国軍機が初めて日本の護衛艦が領海に入ったと主張。 日本は台湾と正式な外交関係を持たないが、現状変更を試みる一方的な行動に反対し、台湾海峡を巡る問題は平和的に解決されるべきだとの立場を取っている。 日本の歴代首相は、台湾海峡危機と自衛隊派遣の可能性を公の場で結び付け語った。高市氏が政治の師と仰ぐ故安倍晋三元首相も、中国の軍艦や海警局の船は尖閣諸島付近への侵入を頻繁に繰り返している。22年には、中国が台湾周辺で数十年ぶりの大規模軍事演習を実施した際、弾道ミサイルが日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下した。「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングなどが現地に工場を設立、または中国企業から製品を調達して日本や海外で販売した。 中国企業は自動車やエレクトロニクスといった高付加価値製品の分野で日本企業と直接競合し始めており、日本は完成品よりも中国への部品供給国としての性格を強めている。三菱自動車や日本製鉄など、一部の日本企業は中国事業から撤退、または縮小している。 さらに改正された反スパイ法など厳格な規制が企業の投資意欲をそぎ、個人も渡航を控える傾向が強まっている。東京エレクトロンやニコンなど日本のハイテク企業は、最先端半導体の製造に必要な装置や化学品の対中輸出を制限する措置の影響を受けている。 中国国営メディアは11月中旬、政府が「実質的な報復に向けた十分な準備を整えた」と伝え、想定される措置として、制裁のほか、経済・外交・防衛関係者の交流停止や貿易制限などが含まれる可能性を示唆した。しかし、中国がレアアース(希土類)供給網での支配的地位を「武器化」する可能性にある。 日中が10年余り前に尖閣諸島を巡り対立した際、中国はレアアース輸出を一時的に停止した。主要銀行を含む一部の国有企業もこの方針に同調し、香港も日本への渡航勧告を更新した。観光庁のデータによれば、7-9月期には外国人旅行者の中で最も多く消費し、訪日客の総消費額2兆1000億円のうち約27%を占めた。全体の37%を占め、最大の出身国だという。 それでも中国は依然として、日本よりも優位に立っているように見える中国だが、慎重な見極めが必要だ。 拙速な強硬策に出た場合、特に重要鉱物への制限を加えたりすれば、日本の同盟国である米国を巻き込む可能性もある。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 日中関係の緊張続く、経済活動への波及リスク高まる-QuickTake