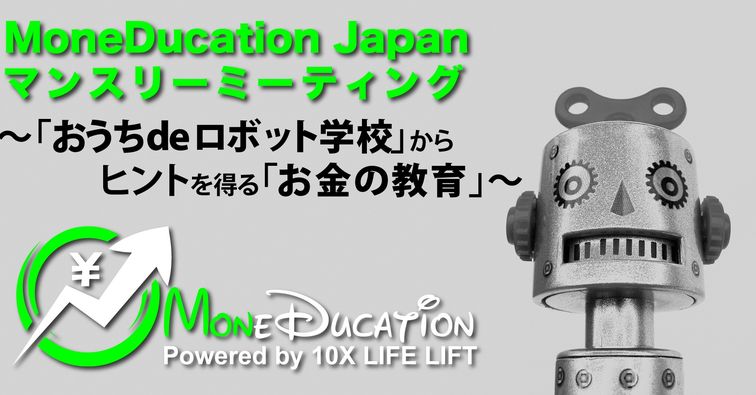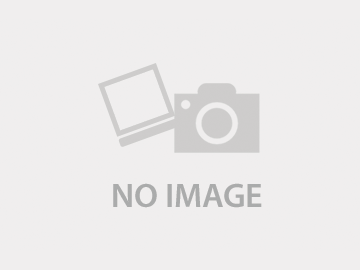日銀の金融機関への付利負担が急増、年内利上げ観測で財務悪化に注目
記事を要約すると以下のとおり。
日本銀行の金融政策運営で政策金利を操作する役割を担う付利制度。日本銀行本店Photographer:ToruHanai/Bloomberg 日銀は昨年3月、マイナス金利解除や長短金利操作の廃止で大規模緩和に終止符を打った。保有長期国債の運用利回り(0.353%)が付利金利を下回る逆ざやも初めて生じた。1%まで利上げが進めば5兆円超に増え、赤字決算も現実味を帯びてくる。政策正常化路線の継続に伴う財務悪化が鮮明になれば、日銀は付利制度の副作用についてより丁寧な説明が必要となりそうだ。一方、利上げ過程で赤字が発生する可能性に言及。長期的には保有国債が金利の高いものに入れ替わるため「収益が戻ってくる」と説明した。 こうした日銀の金融政策運営上の「大きなネックになってくる」とみる。欧米では銀行収益が拡大する中、銀行への超過利潤税導入や中央銀行による利払い停止などが議論になった。実現すればいずれも過去最高となる。 内田副総裁は6月の講演で、バランスシートの縮小を進めている各国の中央銀行の「多くは伝統的な金融調節方法に戻ることはないだろう」と指摘。そう簡単に解消しないことは量的・質的緩和が始まった時から分かりきっていたとし、黒田緩和による「負の遺産に植田日銀がチャレンジしている」との見方を示した。 英国では中央銀行の損失を政府が補てんしている。 ピクテ・ジャパンの市川氏は、これまでは政府の歳入は数兆円単位で減ることになり、「金融政策の決定に影響を与えていく可能性はあるとの見方を示した。」
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 日銀の金融機関への付利負担が急増、年内利上げ観測で財務悪化に注目