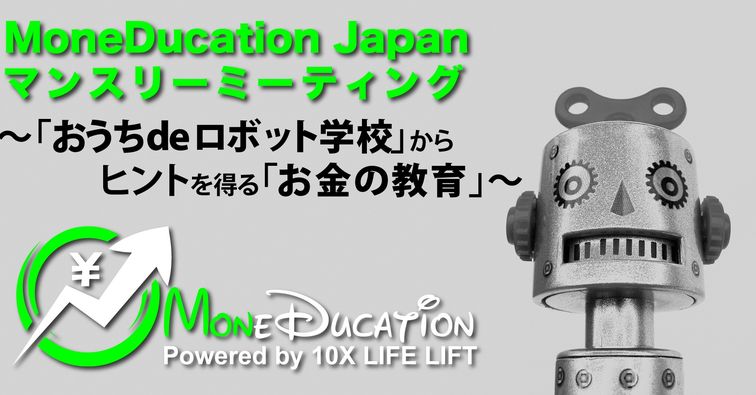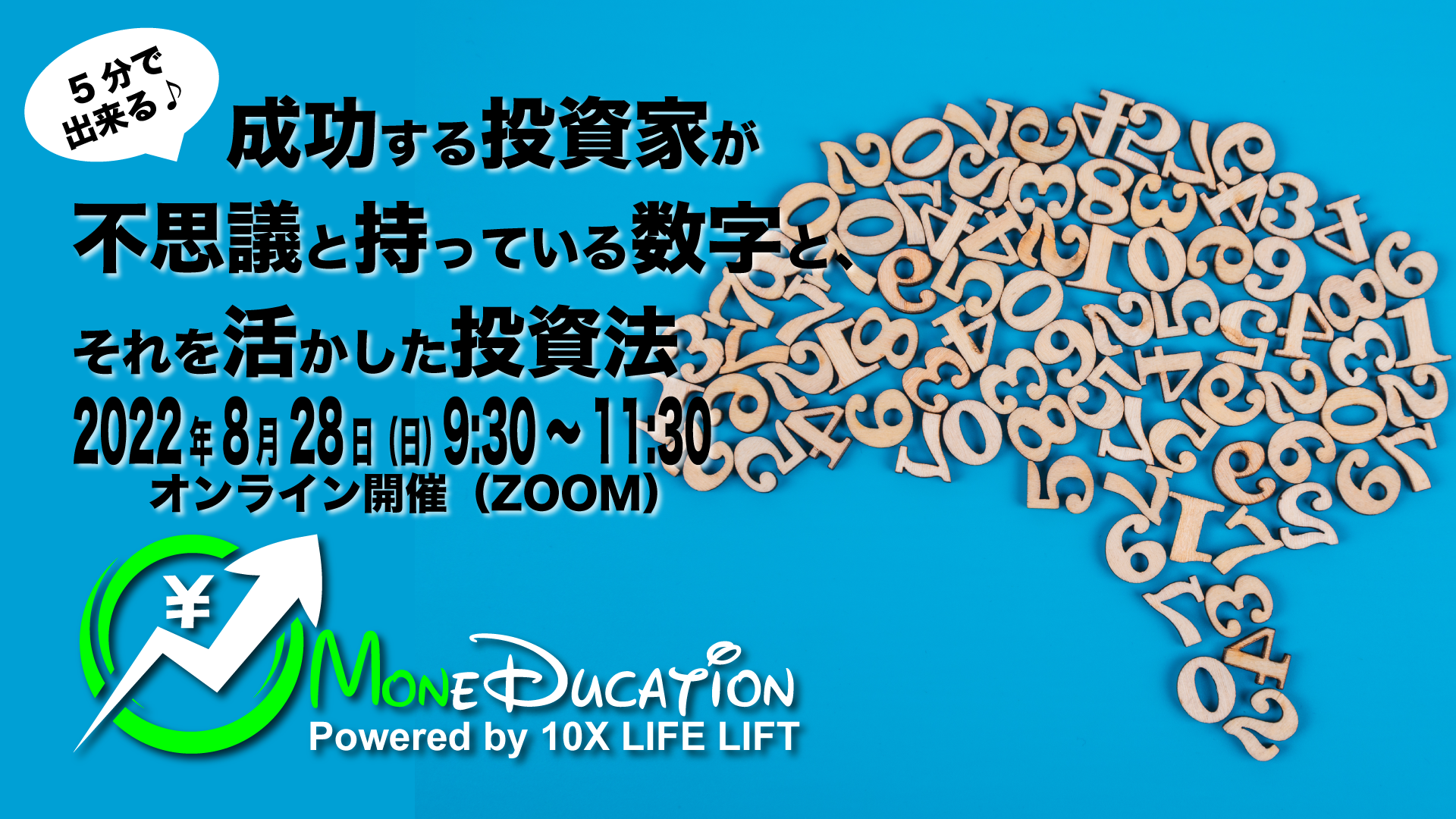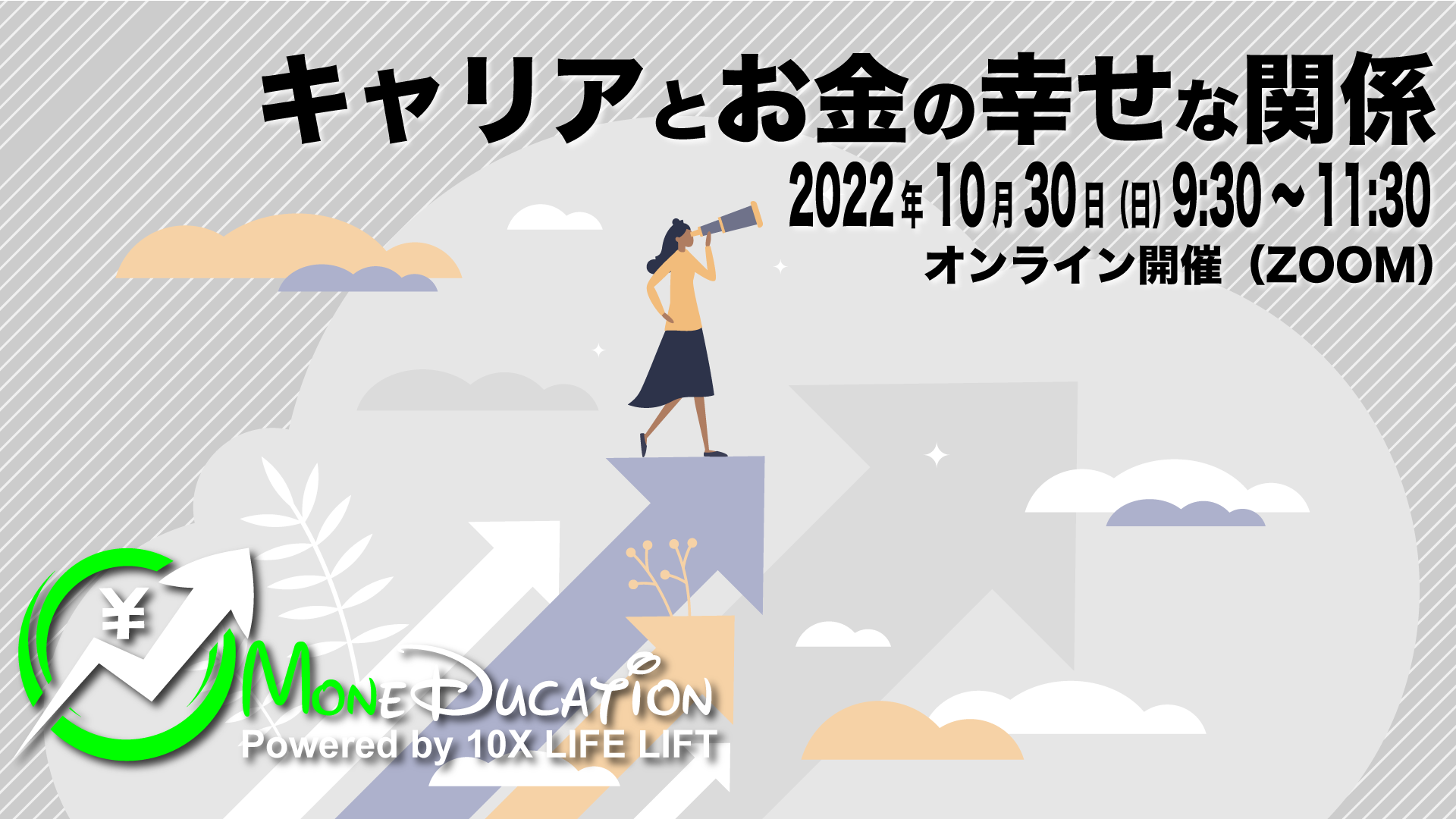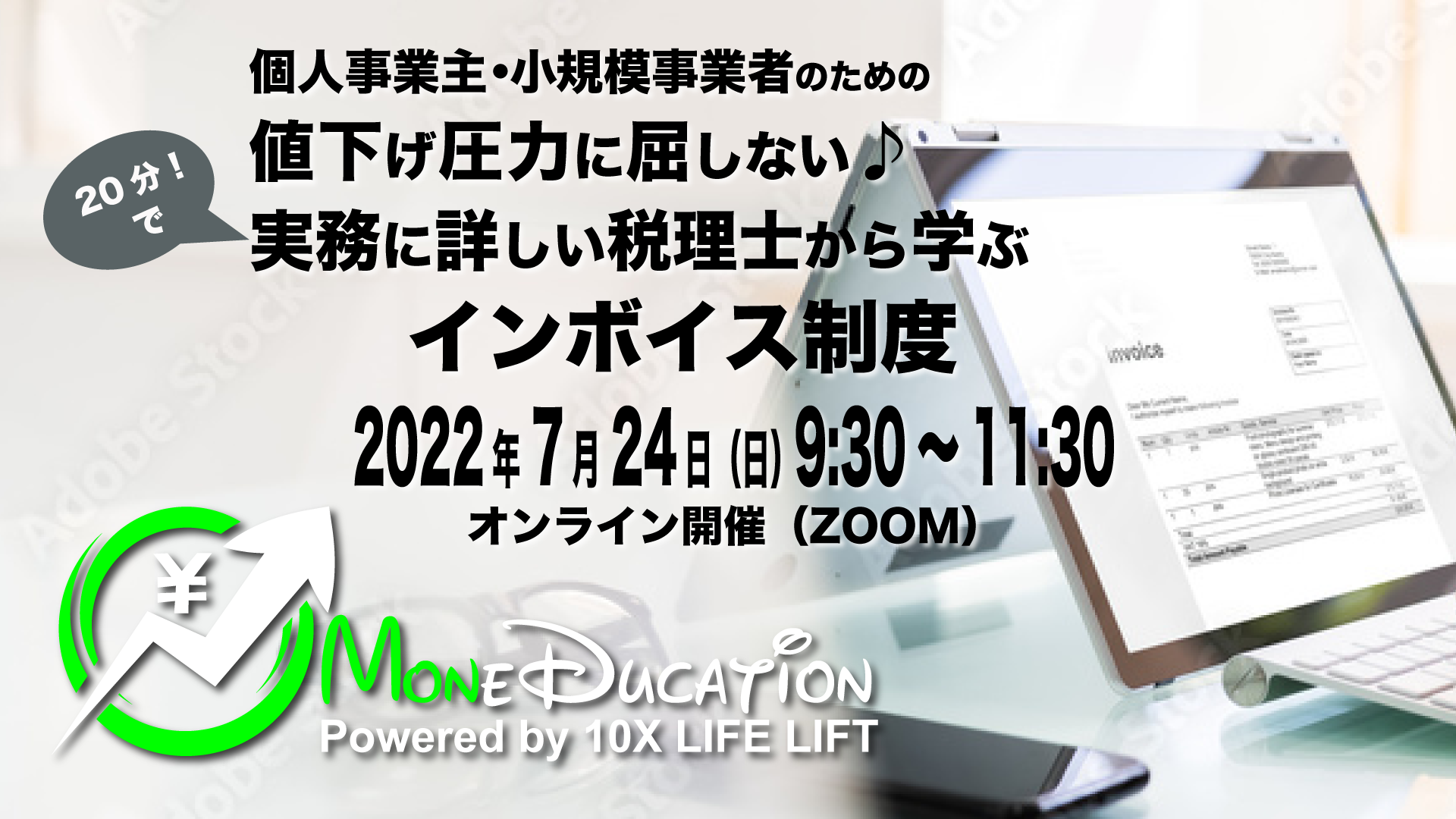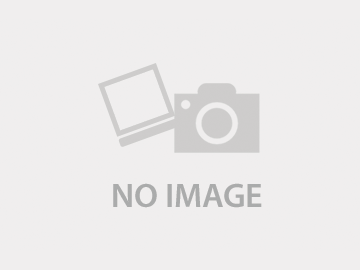AI戦略で米中が激突、技術・インフラ・人材で覇権争い-QuickTake
記事を要約すると以下のとおり。
米国が人工知能(AI)ブームの口火を切ってから、間もなく3年がたつ。背景には、AIの主導権確保を国家目標に掲げる中国政府の後押しがある。オープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者(CEO)は、5月にワシントンで行われた公聴会で「われわれがどれだけ先を行っているのかを正確に測るのは非常に難しい。」AIデータセンターの建設を加速させるための規制緩和や、必要な電力確保に向けた取り組みを打ち出した。技術面での競争 現在のAI時代を形づくる上で、最初の重要な技術的ブレークスルーをもたらしたのは米国だった。ユーザーの代わりにより複雑な作業をこなすエージェントと呼ばれるAIも実用化している。 何よりも注目すべきはオープンソース化を積極的に進めている点だ。一方、オープンAIやアンスロピックなどの米企業は、最上位のクローズドモデルへのアクセスに月額数百ドルを課すことで、AI開発にかかる莫大なコストの回収を図っている。 中国のAIスタートアップの経営者らは、オープンソースこそが新たな市場に迅速に参入し、米国製モデルと競争するための最も現実的な手段だと語っている。 中国のディープシークが今年1月、米国の主要モデルに比べてごくわずかなコストで開発したとされる「R1」モデルを公開した。 バンス米副大統領は7月26日には、李強首相がAIを一部の国だけのものにしないための国際組織を設立すると発表した。中国内陸に広がるAI拠点網、急成長の謎 中国は驚くべき速さでAI戦略を進めている。 米国では、知的財産権、アルゴリズムの偏り、AIによる安全リスクといった論点を巡る議論が、裁判所や企業の会議室、公開フォーラムで活発に行われている。 中国でもAIと著作権に関する法制度は進化途上にある。オープンAIの安全性向上を目的として州ごとにさまざまな規制が導入されている。資金面の勝負 中国のディープシークは、より費用効率の高いAI開発手法を実証してみせたが、それでもAIサービスの構築と維持には莫大な資金が必要だ。 AIブームに至る直前の10年間で、中国政府系ベンチャーキャピタルは、国家発展の中核とされる分野に総額9120億ドルがアリババやテンセント・ホールディングス(騰訊)など大手テクノロジー企業からの拠出と見込まれている。人材面 米国は長年にわたり、海外から研究者やエンジニア、学者を引き付けることでAI人材の獲得競争をリードしてきた。米国では主要AI企業の60%で創業者の少なくとも1人が移民で、AI関連分野の大学院生の70%が留学生とされている。2008年に始まった海外研究者採用プログラム「千人計画」は、ソーシャルメディア、監視カメラ映像、金融取引データなどを国家主導で収集・管理し、AIのための巨大なデータエコシステムを築いてきた。 ただ、中国の閉鎖的かつ検閲されたインターネット環境は弱点にもなり得る。米国主導の輸出規制により、中国はエヌビディアの最先端AIプロセッサへのアクセスを大きく制限されている。トランプ大統領は就任直後、オープンAI、オラクル、ソフトバンクグループによる最大5000億ドル規模のAIインフラ投資構想を支持すると表明した。
[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース AI戦略で米中が激突、技術・インフラ・人材で覇権争い-QuickTake